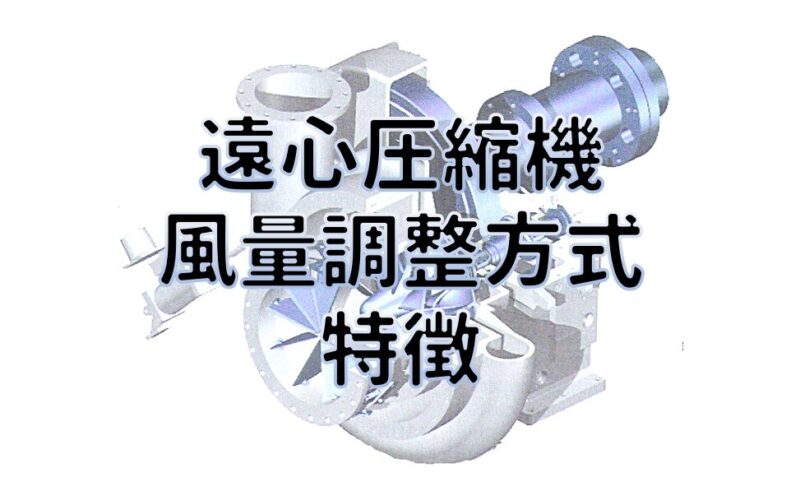
今回の記事では遠心圧縮機の風量調整方式の特徴について解説します。
こちらの記事では往復動圧縮機の容量調整方式について解説しましたが、遠心圧縮機についても適切な調整方式を選定することが重要です。
そこで、本記事では設計やメンテナンスの観点から、遠心圧縮機の風量調整において、各方式の原理・利点・制約を解説します。
合わせて読みたい
・【圧縮機】コンプレッサー(Compressor)の種類と特徴の解説
・【圧縮機】あなたのプラントは大丈夫?遠心コンプレッサー周りのSettle out Pressureの説明・算出方法
・【圧縮機】遠心コンプレッサーのサージングとその対策方法について
・【圧縮機】スピルバック制御とは?往復動圧縮機の運転制御について解説
・【圧縮機】コンプレッサーの設計の留意点について解説
・【圧縮機】往復動コンプレッサーの脈動と振動の低減対策について解説
・【圧縮機】往復動圧縮機の容量調整方式の特徴について解説
・【タービン】化学プラントで使用される蒸気タービンの種類と特徴の解説
・【タービン】蒸気タービンの設計における適用規格と留意点の解説
・【ポンプ/圧縮機】プラントで使用される回転機の駆動源選定の主な検討事項について解説
・【配管】機器周りの配管レイアウト設計の留意点について解説
・【配管】プラントの音響疲労破壊とは?音響レベルの計算方法と対策
・【配管】プラントの配管振動を引き起こす主な原因とその対策について
・どんな機器に予備機は必要?プラント機器の予備機の考え方について解説
速度制御(回転数変化)

最も基本的な方式で、駆動源の回転数そのものを変えることで風量・風圧を調整します。主な特徴は以下の通りです。
速度制御(回転数変化)方式の特徴
- 蒸気タービン・ガスタービン・可変速電動機など、速度可変型原動機との組合せで有効
- 定速電動機でも流体継手の導入によって速度制御が可能
- 制御対象(風量/風圧)と設定値との差を検出し、原動機または継手を操作して偏差をゼロに近づける
ただし、この方式はサージング限界より少風量側の領域では安定性が低下するため、補助的な放風・バイパス制御が必要となります。
吐出弁制御
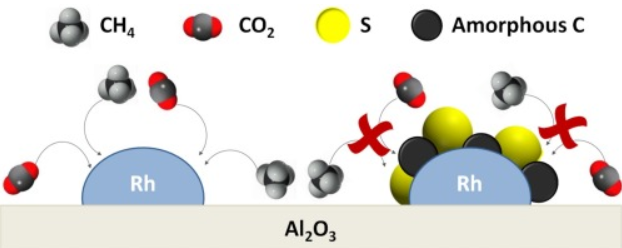
吐出圧力や送風量を制御する目的で吐出側の弁を操作する方法です。主な特徴は以下の通りです。
吐出弁制御方式の特徴
- 回転数一定時に用いられ、簡易で安価な調整方式
- 調整下限がサージング限界で制約されるため、広範囲の調整には不向き
この方式は、小型の圧縮機や高ヘッドの圧縮機での簡易調整には便利ですが、制御幅の狭さに注意が必要です。
吸込弁制御(吸込ダンパ調整)

吸込管にダンパを設け、その開度を変えることで吸込流量や圧力を調整する方法です。主な特徴は以下の通りです。
吸込弁制御(吸込ダンパ調整)方式の特徴
- 吸込絞りにより吸込比重量を変化させる
- 結果として吐出圧力または風量の変化が可能
- 吐出弁制御方式と比べて、サージング限界がより小風量側に移動し、制御範囲が広くなる
ただし、ダンパを設置することにより、圧力損失が大きくなって全体の効率が低下することや、吸込側での摩耗や固着のトラブルのリスクが高くなるデメリットがあります。
また、ダンパは一般的に応答が遅いので、プロセスの動的変化に制御が追い付かない場合はプラント全体の運転安定性に影響することがあります。
入口案内羽根制御(Inlet Guide Vane制御)

第1段羽根車の直前に可動式案内羽根(Inlet Guide Vane)を設けて、角度を変えて制御する方式です。
多くの遠心式送風機・圧縮機に採用されています。主な特徴は以下の通りです。
入口案内羽根制御(Inlet Guide Vane制御)方式の特徴
- 案内羽根で流入気流に旋回を与え、羽根車への入口条件を制御
- 吐出圧は若干低下するが、吸込絞りよりも軸動力を低減できる
- サージング限界も小風量側へ移動するため、制御範囲拡大に貢献
ただし、この方式は羽根全開時の損失が大きくなる場合があり、最高効率が低下する点に注意が必要です。
ディフューザ羽根制御

吐出側に設けるディフューザ羽根の角度調整により、吐出圧や風量を変える方式です。
基本的にこの方式のみを採用することはなく、他の方式と組み合わせることになります。この方式の特徴は以下の通りです。
ディフューザー羽根制御方式の特徴
- ディフューザ羽根によって風圧曲線の傾斜が強くなり、サージング限界風量は増加傾向
- 羽根角度が調整可能であれば、広い風量制御範囲が実現可能
- 吐出圧一定で風量を変化させたい用途に有効
ただし、この方式を採用することにより、構造が複雑となり保守点検の工数が増えるため、導入判断には慎重さが求められます。
静翼角度制御
この方式は軸流型送風機・圧縮機の風量調整方式です。静翼の角度を可変に設計することで制御範囲を広げる方式です。
この方式の特徴は以下の通りです。
静翼角度制御方式の特徴
- 静翼のうち入口案内翼のみ可変の場合:約7%の風量調整が可能
- 数段/全段を可変にすると最大50%程度までの制御範囲が可能
- 回転数制御との併用によりさらに調整性能を強化できる
効率を大きく損なうことなく調整範囲が広げられるため、用途に応じて段階的な可変設計が有効です。
動翼角度制御
静翼角度制御方式同様、軸流型送風機・圧縮機の風量制御方式で、動翼自体の角度を制御する方式です。
幅広い作動範囲に対応できることから、軸流型送風機・圧縮機ではこの方式が最も広く採用されています。
この方式の特徴は以下の通りです。
動翼角度制御方式の特徴
- 外部から電気・油圧により動翼の角度変更が可能
- 最も広範囲な制御が可能な方式で、軸流機に特に有効
ただし、回転中の動翼角度を制御するため、高い信頼性と精密な構造が要求されることに加え、保守性にも配慮が必要です。
運転台数の変更(並列構成)

複数台の送風機・圧縮機を並列に設置し、運転台数の増減で全体の風量を調整する方式です。
この方式の特徴は以下の通りです。
運転台数の変更(並列構成方式)の特徴
- 軸流型では、自動車トンネルなど、大風量用途で一般的に採用されている
- 段階的な調整しかできないため、細かい風量制御には不向き
- 必要に応じて他の角度制御や速度制御との組合せが有効
ただし、複数台設置することによって、全体の機器コストが増加する他、台数制御を行うためにはPLCやDCSなどのロジックの設計が必要となります。
まとめ
遠心圧縮機の容量調整では、「制御範囲」「サージング限界」「効率」「構造・保守性」などを総合的に判断することが求められます。
各方式は単独でも機能しますが、組み合わせることで制御精度と運転安定性が高まるケースも多くあります。
そのため、設計段階から運用目的に応じて最適な制御体系を構築していくことが、長期的な設備信頼性と省エネルギーにつながると言えます。

