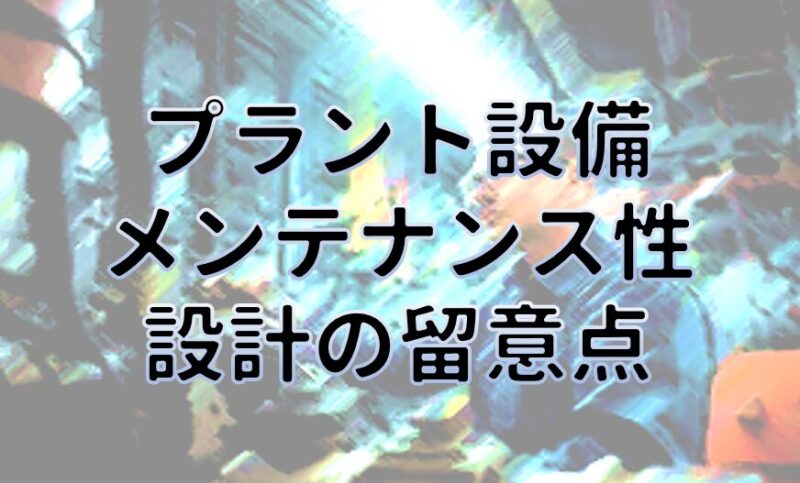
今回の記事ではメンテナンスを考慮した設備設計の考え方について解説します。
プラントのメンテナンス作業のための設備停止期間が長くなると、プラントの操業計画に大きく影響を与えてしまうため、メンテナンス作業は行いやすく、かつ短い期間で終わることが望ましいです。
メンテナンス作業のしやすさを確保するためには、設備の設計段階でメンテナンスを実施するための必要事項を反映しておく必要があります。
次項から、基本的な考え方と、各機器のメンテナンスを考慮した設計の留意点について解説します。
合わせて読みたい
・どんな機器に予備機は必要?プラント機器の予備機の考え方について解説
・プラントで使用される泡消火薬剤の分類と特徴について解説
・化学プラントにおける各機器の一般的な省エネルギー対策
・化学プラントの能力増強の考え方と検討事例について
・プラントの配置計画|レイアウト検討のポイントと注意点
・触媒の充填方法を徹底解説|固定床・管型反応器への触媒充填手順と注意点まとめ
・【触媒】触媒劣化対策について解説/原因究明から設計改善まで
・【配管】プラント建設後の配管はどうやって洗浄する?配管洗浄方法の解説
・【配管】ラインチェックとは?プラント配管施工時の確認項目について解説
・【配管】プラントの配管設計における一般的な留意事項について解説
・【配管】プラントにおける配管溶接の特徴について解説
・【配管】プラントのボルト結合フランジにおける締め付け管理について解説
・【計装】プラント建設現場における計装設備のループチェック・検査要領について解説
・【計装】設計に注意を要する調節弁の事例について解説
・【ポンプ】遠心ポンプの設計、使用上の留意点について解説
・【ポンプ】遠心ポンプの吸込配管の必要直管長について解説
・【圧縮機】コンプレッサーの設計の留意点について解説
・【圧縮機】往復動コンプレッサーの脈動と振動の低減対策について解説
基本的な考え方

一般に、プラントのメンテナンス性を確保するために必要な考慮事項は以下の通りです。
プラントのメンテナンス性の考慮事項
・ 運転思想、保全思想、安全思想、設計思想が整合している。
・ 予備機の数がメンテナンス作業をするうえで適切である。
・ 機器増設の場合、既設の機器と同等の機器を選定する。
・ 複数の機器で共有できる部品を選定する。
・ 機器の部品交換がモジュール単位で実施可能である。
・ 機器の移動、据え付け、分解、組立が容易である。
・ 機器内部へのアクセスが容易である。
・ 機器の状態監視や異常診断をできるようにする。
・ 機器周辺の作業環境、作業スペースが適切である。
・ 機器の保全や検査に関する書類が整理されている。
・ 作業場や倉庫などの環境が整っている。
設計検討の考え方

設計思想、運転思想との整合性
プラントの設計、運転においては、運転思想、保全思想、安全思想、設計思想が整合しておかなければなりません。
具体的には、そのプラントに適用される法規や社内のHSE基準を遵守する他、保全要因、設備、輸送手段だとが確保されている必要があります。
冗長性
設備の冗長性を検討する際には、信頼性だけでなく、メンテナンス性も考慮しなければなりません。
具体的には以下の通りです。
冗長性の検討で考慮すべき項目
・ 予備機の数と単体の機器能力の組み合わせ(50%×2基など)
・ ホット/コールドスタンバイの必要性
・ メンテナンス作業時の全体/部分シャットダウンの必要性
・ 常備する予備品の必要性
予備機の思想についてはこちらの記事も合わせて参照ください。
機器の選定
機器の選定では、メンテナンス性の観点から、実績があり、信頼性、汎用性、拡張性が高いことが要求されます。
また、年間のプラント運転を通して、メンテナンス作業が最小限であり、コストも安価で、購入後の機器ベンダーのサポートが充実していることが望ましいです。
アクセス性
機器のメンテナンス作業がしやすいように、アクセス性も重要な要素です。
以下にアクセスの検討で考慮必要な項目例を記載します。
アクセス性検討で考慮すべき項目
・ 問題ない作業高さで、必要な保護具も完備されている。
・ 現場巡視経路からのアクセス性が良いこと。
・ 周辺機器を分解しなくても、メンテナンス対象機器にアクセスできる。
・ 解放点検時の取り外した部品置き場が近くにある。
・ メンテナンスのための備品、工具の置き場が近くに確保されている。
・ クレーンやトラックの寄り付きが容易にできる。
・ メンテナンス対象機器の縁切りや不活性ガスの置換が容易である。
・ チェーンブロックやトロリーなどの常用設備でないものは取り外し可能で、保管エリアに置くことができる。
・ ホースステーション(蒸気、雑用空気、水、窒素)及びそのノズルが近くにある。
状態監視
故障等によるプラント運転への影響を最小化するために、機器の状態を常時監視する必要があります。
監視装置の一例として以下のものがあります。
監視装置
・ プローブやクーポンなどの腐食モニタリングシステム
・ 振動監視装置
・ 運転パラメータの測定装置(流量、温度、圧力など)
・ ガス検知器
機器の識別
メンテナンス対象物の管理のしやすさの観点から、機器、計器、バルブ類はタグ付けして明示しておく必要があります。
ユニット機器(ポンプ、ドラム、配管などを一つをパッケージとしてベンダーに発注するもの)については、パッケージそのものをタグ付けし、ユニット機器内部の機器、計器、弁についてもタグ付けをします。
タグ付けの際は、将来増設を考慮してタグの桁数に余裕を持たせたり、タグの文字は読みやすく容易に消えない方法で表示する、などの配慮が必要です。
つり上げ装置

プラントのメンテナンスでは、クレーン、ホイスト、チェーンブロックなどのつり上げ装置を使用することがほとんどです。
ここではこれらのつり上げ装置の選定や設計の留意点について解説します。
つり上げ、運搬装置の選定
つり上げ装置選定の留意点
・ つり上げ、運搬装置は、常設、仮設を問わず取り外し可能にできるようにする。
・ つり上げ、運搬装置はそれ自身のメンテナンス作業がしやすいようにする。
・ 運搬経路や作業場所を決める際は、個別作業ごとに検討する。
・ 運搬経路や作業場所は明確に規定す、作業床に最大許容加重がある場合は、床に作業可能エリアをマーキングする。
・ 移動式クレーンのアウトリガー接地箇所の許容加重、埋設配管有無、コンクリート強度などを確認しておく
・ 移動式クレーンのアクセス性が悪い場合は、常設の設備を採用する。
・ 高所作業の場合や機器を長時間停止できない場合は、使用頻度が少なくても、動力装置を持つ装置を採用する。
つり上げ、運搬装置は、使用頻度と荷重を考慮して選定する必要があります。
選定例として以下の通りです。
<荷重が1ton未満>
使用頻度が多い場合は常設ビーム&ホイスト、或いは常設ビーム&チェーンブロックを採用します。
使用頻度が1年以下で少ない場合は仮設門型ビーム&チェーンブロックを検討します。
<荷重が1ton~10ton>
使用頻度が多い場合は常設ビーム&ホイスト、常設ビーム&チェーンブロックの他、頻繁に使用する場合(1か月複数回)は天井走行クレーンの採用を検討します。
使用頻度が1年以下で少ない場合は仮設門型ビーム&チェーンブロックの他、重量に応じて常設ビーム&チェーンブロックを採用します。
<荷重が10ton以上>
使用頻度によらず基本的に天井走行クレーンを採用します。
その他考慮事項
運搬装置については、機器のみならず、プラントの現場に持ち込まれる薬品、備品についても可能な限り検討する必要があります。
クレーンについては、メンテナンスが容易な構造とし、可能な限り定期点検作業時に仮設足場が不要な構造とします。
また、周囲環境による腐食リスクが高く、かつ使用頻度が少ない場合は、特殊工具が無くても簡単に脱着できる耐候カバーの設置を検討する必要があります。
ホイストについては、レールを許容外の荷重で使用しないように、レールの容易に視認できる箇所に許容加重をマーキングする必要があります。
特定の機器の設計基準

配管
配管設計では以下の項目について検討する必要があります。
配管設計の検討項目
・ パイプサポートは配管本体の摩耗、腐食を考慮した構造とする。
・ 機器周りの配管レイアウトには余裕をもたせて、機器の据え付け時に過大な応力がかからないように考慮する。
・ バルブの取り外しを考慮し、配管にはある程度の余裕、柔軟性をもたせる。
・ 配管のポケット(流れが滞留する部分)を極力つくらないようにする。
・ 塗装や検査がやりやすいよう、直近の壁や床からある程度話した場所に配管をレイアウトする。
また、配管に対しては、プロセス上、安全面での要求により保温、保冷施工を行うことがありますが、メンテナンス性の観点では、そのような保温材、保冷材の施工は最小限とし、必要な箇所にのみ設置する必要があります。
また、保温材を施工する際の留意点を以下に記します。
保温材施工の留意点
・ 断熱材下腐食のリスクを下げるため、火傷防止を目的とする場合は、保温材ではなくパンチングメタル等の他の手段を検討する。
・ 保温材は可能な限り取り外しできる構造とする。
・ フランジなど、定期的に分解作業が発生する箇所については外装材をクランプ止めとして取り外しできる構造にする。
・ 可燃性流体配管の保温施工では、フランジ部でのガス漏れに配慮する。(ガス検知用チューブの設置など)
・ リベット止めは用いず、ビス止めを採用する。
・ 保温材の検査窓は雨水が入らない構造とする。
・ 建設時は、耐圧、気密試験が完了するまでは保温材を施工しない。
・ バルブの操作ハンドルの可動部や計器表示部など、目視が必要な箇所については操作性、視認性を損なわないようにする。
バルブ
原則として床やプラットフォームからのアクセスが容易な場所にバルブを設置します。ただし、建設・改造工事で使用した捨て弁や将来増設用の弁、その他定期的な使用計画が無い弁については、アクセス性の考慮は不要です。
定期的にグリスの注入が必要なバルブ類には、保温材を分解しなくてもグリス注入できるよう、延長グリスニップルの設置を検討します。
調節弁については、調節弁の重要度やサイズなどを考慮して、バイパスラインの設置を検討します。
安全弁については、プラント内の作業場に安全弁テストベンチの設置を検討する必要があります。
圧力容器
圧力容器の配置を決める際は、外観検査や再塗装作業をするスペースや、内部部品の取り外しや検査のためのスペースを考慮する必要があります。
フィルターについては、プラント運転を継続しながらフィルターの解放、清掃を行う場合があります。その場合はフィルターの予備機を設置します。
また、想定するフィルターの汚れ度合いによっては、差圧を設置し汚れ度合いを監視する必要があります。
予備機と切り替える場合は、適切なインターロック設置や流れを阻害しないような構成を検討します。
熱交換器
メンテナンス性の観点からの熱交換器設計の留意点は以下の通りです。
熱交換器設計の留意点
・ 耐圧部の溶接線を、ブラケットや当て板で隠さないようにする。
・ チューブバンドルの引き抜き、挿入のため、熱交換器上部にホイストレールの設置を検討する。
・ 同様にチューブバンドル引き抜き、挿入用にチェーンブロックの指示店を考慮する。このときチューブバンドルにはアイボルトの設置を考慮する。
・ チャンネルカバーを取り外しても、チューブシートとシェルが緩まない構造を考慮する。
・ チャンネルカバーの取り外しが容易にできるように、接続配管にはスプール(リムーバルスプール)を設置する。
・ 熱交換器が多段になる場合は、直接ノズル同士を接続するのではなく、スプール配管などを挿入する。
・ チューブバンドルの洗い場への移動計画や排水計画を検討しておく。
フレアスタック、ベントスタック
プラントの運転中にフレアスタックやベントスタックのメンテナンスを想定する場合は、プラントの運転ロード変更や停止時に発生する放散ガスの代替処理案を検討する必要があります。
また、フレアスタックの設計においては、Topにあるパイロットバーナーのメンテナンス、交換を想定し、作業に必要なクレーンのサイズや設置場所について確認しておかなければなりません。
回転機
ポンプや圧縮機などの回転機については、故障リスクが高いことから、特別な配慮が必要です。
以下のような運転パラメータの監視の他、寒冷地での積雪や沿岸部における塩害対策も必要です。
監視必要な回転機の運転パラメータ
・ 運転時間
・ 振動
・ 軸変位
・ トルク
・ フィルターの差圧
メンテナンス性の観点からのポンプ設計の留意点は以下の通りです。
ポンプ設計の留意点
・ ポンプの取り外しを考慮し、必要に応じて吸込み/吐出配管にスプール配管を設ける
・ カップリングカバーには手回しが行えるように開閉式窓を設ける
・ 必要に応じてポンプ、モーター上部にホイストレールを設ける
・ 運転中でもグリスアップができるようにグリスノズルを設ける
・ モーターが竪型の場合、屋外では雨水侵入対策としてファンカバーを設ける
メンテナンス性の観点からの圧縮機設計の留意点は以下の通りです。
圧縮機設計の留意点
・ オーバーホールを考慮し、圧縮機本体近傍に部品を仮置きできるスペースを設ける
・ 圧縮機本体のメンテナンス用のクレーンを設ける
・ メンテナンスステージは吸吐弁の取り付け、取り外しを考慮した高さとする
空冷式熱交換器(Air fin Cooler)は熱交換器の一種ですが、回転機構を持つため、回転機としてのメンテナンス性の観点からの留意事項は以下の通りです。
空冷式熱交換器設計の留意点
・ ファン、モーター用ベアリングに雨水が侵入しないよう、不倫ガー、水抜き穴などの対策を講じる
・ モーターの取り付け、取り外し用フック(吊り金具)をステージ、ユニットに設ける
・ 運転中でもグリスアップができるように、グリスノズル位置を考慮する。
ガス検知器、火災報知器
ガス検知器や火災報知器のシステムは信頼性が高く、メンテナンス頻度が低いものを選定します。
特に以下の項目は重要です。
ガス検知器、火災報知器の留意点
・ ガス検知器のフィルター交換が容易であること
・ 故障モニタリング機能がついていること
これらの検知器は、校正作業がしやすいように、アクセスしやすい場所に設置します。また、監視部(監視警報盤)の設置場所は視認性がよく、アクセスしやすい場所に設置します。
アクセスが困難な場所に設置する検知器(高所や高温など)については、仮設足場を設置しなくても検査できる方法を検討します。


